
台湾や中国に駐在していた時に、子どもに中国語を習わせていた。
せっかくなので、日本に帰国後も忘れないようにしたいけど、帰国後もうまく続けるにはどうしたらいいかな?
という疑問に、日本でも子どもの中国語力をキープするためにできる方法をお伝えします。
ちなみに、本記事を書いている私は、2016年から3年間、3人の子どもと一緒に台湾・台北に住んでいました。

台湾に引っ越した時の子どもの年齢は、長女(9歳)、次女(5歳)、長男(1歳半)。
すでに4年生だった長女は、ちょっと外国語に構える年齢。
中国語を積極的に習いたい、とまではなりませんでした。
英語は好きだったので、無理して中国語まで習うことはせず、英語だけ習っていました。
反対に、次女と長男は地元の幼稚園に通ったこともあり、すぐに中国語になじんで同い年の台湾の子たちと話せるくらいになっていました。
加えて次女は、小学校1年生になった時から公文で中国語を勉強。
台湾の公文などについては、こちらの記事をどうぞ⬇️
帰国後、長男はまだ4歳なので、日本でレッスンできるような環境になく、いったん保留(ほぼ中国語を忘れていますが、仕方ないかなと思っています)。
基本ができていた次女だけは、中国語力をキープできるようにぼちぼち習っているという状況です。
この記事では、主に我が家の次女(現在小学3年生)の中国語の勉強方法から、台湾・中国在住後も、中国語力を維持する方法をお伝えします。
※本記事で使っている「中国語」は、「普通語(pu tong hua)」と言われている北京語がベースになった中国国内で共通語として使われている言葉を指しています。台湾で話されている「中国語」は、「普通語」とほぼ同じですが、単語など違う部分も多いので区別して「台湾華語」と言われています。
本記事の内容
- うちの子がやっている中国語の勉強方法
- マイルストーンを決める
- なぜ中国語を習うのかを親自身の中で明確にする
- 子どもが楽しく学べているかが一番重要
うちの子がやっている中国語の勉強方法
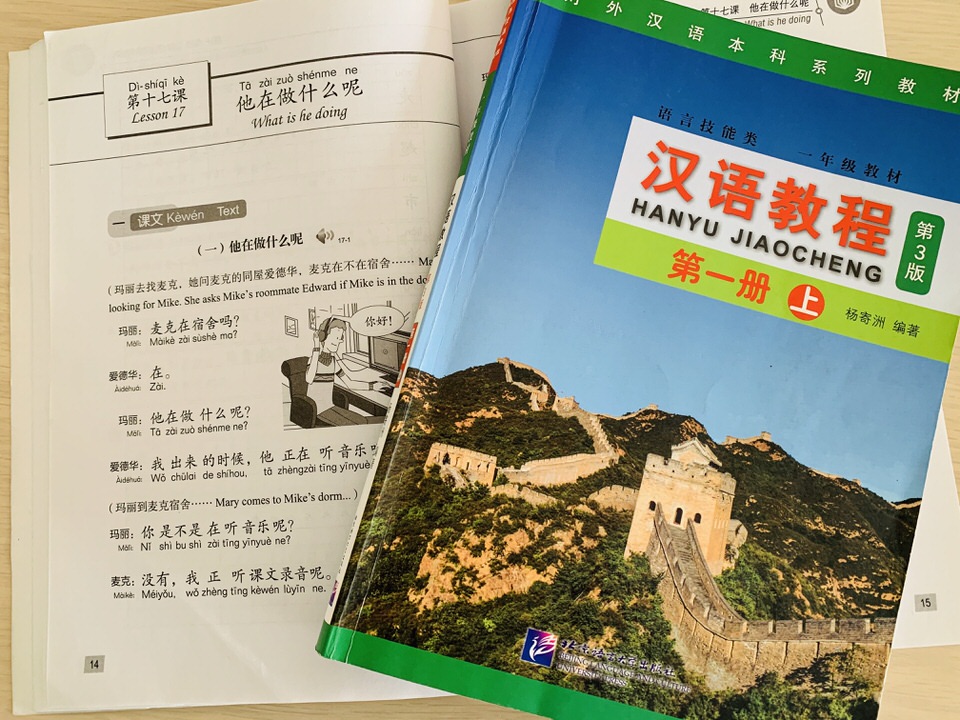
①中国語レッスン(週1回)
週1回、マンツーマンで中国語のレッスンに通っています。
英語と違って、そもそも中国語を習える教室は限られているもの。
しかも、子どもの場合、同じようなレベルの子どもを複数人集めるのはほとんど無理なので、個人レッスンにならざるを得ません。
もちろん、その分レッスン代も高くつきます😭
日本で週1回以上通うのは、なかなかお財布が許してくれません。
我が家の場合、ちょうど通える範囲に中国語レッスンを受けられる教室があったのでよかったですが、通える範囲にない場合、こういったオンラインの中国語レッスンという手もありますね。
500万人以上が使っている!オンライン言語学習ツール【italki】うちの次女も、もう少し基礎固めをしてから、たくさん話す練習をするには、オンラインレッスンも取り入れようと思っています。
②HSK(漢語水平考試)受験
外国語の勉強で自分のレベルアップを測るには、検定試験が一つの指標になります。
中国語は日本国内でも勉強している人が多い外国語の一つ。
日本で受けられる検定試験も4種類あります。
その中で、年間の実施回数が多く、受験者数も多いメインどころは、中国語検定とHSK。
- 中国語検定(中検):日本中国語検定協会が実施している検定
- HSK(漢語水平考試):中国政府が実施している検定
HSKの方が、かなり初歩のレベルからあるので、うちの次女のような小さい子が受けるのにはちょうどいい試験です。
漢字検定や算数検定など、子どもにとって何かに合格するというのは、自信にもやる気にもつながるので、子どものレベルに合わせた検定はうまく利用したいもの。
次女も先日初めてHSK1級を受験してみました。
今日は次女がHSK(漢語水平考試)という中国語の検定を受けています。
— ナオ@三児の母(13歳・9歳・5歳)+夫(自営)の秘書兼妻 (@naohana77) January 12, 2020
中国政府がやってる検定なので、ムムムと思いつつ😑次女の中国語力キープ、力試しで自信をつけることを目的に受検。 #台湾 で中国語をやってたので簡体字、拼音を覚え直して勉強中ですが、繁体字を忘れないように教えてます。 pic.twitter.com/r79CA5Cy94
レベル的には全然難しくないのですが、他の受験生は大学生や大人ばかり。
その中で受けるのでかなり緊張していましたが、受けた後は、とても自信になったみたいです。
過去問を見てみると、HSK2級もレベル的には受けられるので、次回受ける予定です。
③中国語・英語のアニメDVD
台湾から帰ってくる時に、買いだめしたものの一つが、ディズニー映画やドラえもんなどのDVD(海賊版じゃありませんよ😁)。

台湾で売っているDVDなので、中国語・英語の2音声もしくは、中国語のみなのです。

家庭でお手軽に中国語に触れられてグッド。
好きなアニメなので、中国語をほぼ忘れている長男も一緒に喜んで見ていて、見ている間は中国語モード(?)になっています。
ただ、最近は少し飽きてきたので、そろそろ新しいDVDを仕入れたいなと思っているところです。
④台湾の友達と接点を持ち続ける

これが一番重要かなと思いますが、台湾のお友達と接点を持ち続けることが何よりの中国語の勉強。
結局、言葉は誰かとコミュニケーションを取るためにあります。
どんなに勉強していても使う機会がなければ、だんだんモチベーションも下がります。
今は、SNSで簡単につながっていられる時代。
しかも台湾人は日本によく遊びにきてくれるので(笑)。
台湾でできたお友達とのご縁をこれからも大切にしたいと思います。
マイルストーンを決める

小さいうちから外国語をする場合、高校生や大学生のように必要性に駆られているわけではありません。
だから、いつまでに、どれくらいのレベルになれたらいいねという具体的なステップを見せてあげると、子どもにも分かりやすく、やる気になれます。
先ほど書いたように、漢検や数検と同じ。
一応、我が家でざっくり決めているのは、小学生の間に、
HSK4級(できれば5級)
もしくは
中国語検定3級
まで取得できたらいいね、と目標にしています。
中国語検定3級は、大学生で1年間普通に勉強すれば取れるレベルです。
(話すのはまた別ですが)
今のペースであれば、そんなに無理なくできる目標設定かなと思っています。
今後の取り組み方で変わってくるので、その辺も柔軟に見ていきます。
「なぜ中国語を習うのか」を親自身の中で明確にする

子どもが習い事を続けるためには、親の方でも、「なぜその習い事をするのか」ということを明確にした方がいいと思います。
なぜなら、好きなことでも、子どもがいつも調子良くできるとは限らないから。
親の中で軸がないと、子どもがつまずいた時にうまくサポートできません。
そもそも、習い事はお金も時間もかかるものなので、よく吟味したいですし、特に変わった習い事の場合、なぜそれをやるのかは続けるために重要です。
うちの次女が引き続き中国語を習っているのは、
- ①台湾生活の中で、次女が外国語好きだと分かったから、強みを伸ばしたい。
- ②英語は当たり前の時代。英語プラス他の言語ができると強い。
- ③発音は子どものうちの方が身につきやすい
- ④中国は「異形の大国」。台湾は日本の最重要パートナー。二つの国とコミュニケーションが取れる言葉が中国語であり、日本人で中国語人材は重要。
こういった理由です。
一番重要なのは、①次女が好きだから。
ここが基本です。
その上で、②、③があります。
そして④ですが、これは、私自身が大学時代に中国語を勉強していたということも関係あります。
中国との付き合い方、(単に「友好」が通じる国ではないという意味で)中国に関する正しい理解が、日本人として重要だと思っています。
特に中国(中華人民共和国)が、今後どのような政治体制になるかはわかりません。
少なくとも、今のところ、自由と民主主義の国ではありません。
そこを理解していなくて、経済的な関係だけで中国を重視すると、判断を間違います。
翻って、台湾は自由と民主主義の国家であり、日本にとって最重要パートナー。
個人レベルでも、台湾の友人たちとコミュニケーションするには、中国語を話せる方がもちろん深まります。
うちの次女が、将来どんな仕事をするのかは、もちろんわかりません。
親の私たちが決めることでもありません。
でも、どんな分野であっても、中国語ができることで、日本に、世界に貢献できる可能性は高められます。
小さいうちからコツコツ身につけた中国語が、次女の人生で役に立ち、願わくは世の中の役に立つ人になっていってくれたらいいなと。
もし仮に、直接中国語を使うような仕事ではなかったとしても、中国語を通して学んだことは、必ず生きると思っています。
子どもが楽しく学べているかが一番重要
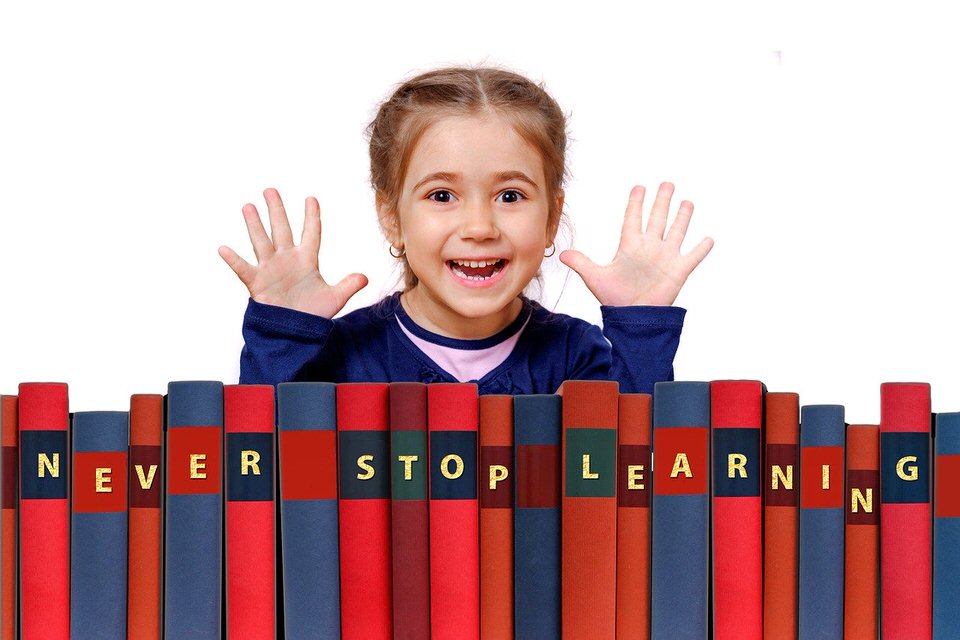
子どもの教育は親の責任です。
なぜなら子どもは、中学生くらいになるまでは、自分で自分の教育環境を選ぶことができないからです。
中学受験は親の意志だと言われるのはそのためです。
もちろん、小さいうちから「これが好き!」「この勉強をしたい!」とはっきり意識できているお子さんもいます。
その場合、むしろ、その強みを伸ばしてあげられるか、親が気づけるかが大事でしょう。
いずれにしても、子どもの教育に関して親の影響が大きいことは確か。
中国語を習うことは、英語を習うよりも、まだ特殊だと思います。
だからこそ、先ほど書いたように、親が明確に目的を意識していることが大事です。
そしてそれ以上に、子どもが楽しく勉強できるようにサポートしてあげることが重要です。
やらされている状態では、中国語の力が伸びないばかりか、外国語を勉強することが嫌になってしまいかねません。
うちの次女は、幸いなことに、台湾にいる時に楽しく中国語を学べました。
そして、外国語でいろんな人とコミュニケーションをとることは楽しい!と思っていることを、親の私たちから見ても感じました。
だから、日本に帰ってきてからも、中国語を続けて勉強しようと本人も自然に思えたと思います。
日本に帰国後もうまく継続できるかは、現地にいる時から始まっていると思います。
反対にいうと、現地で楽しくできていたのであれば、帰国後、なかなか金銭的にも時間的にも大変ではありますが、少しでも継続できる環境を親が整えてあげることで、子どもの可能性を広げてあげられます。
ただ、外国語の習得は、母語(うちの場合日本語)の力と大きな関係があるので、決して比重が母語と反対になってはいけません。
我が家では日本語の力をちゃんと伸ばすことが大前提で、その上で中国語と考えています。
細く、長く、無理なく続けていけるようにしたいと思っています。
子どもの中国語力をキープする方法まとめ
本記事では、我が家の次女(現在小学3年生)の中国語の勉強方法から、台湾・中国在住後も、中国語力を維持する方法をお伝えしました。
■うちの子がやっている中国語の勉強方法
- ①中国語レッスン(週1回)
- ②HSK(中国語の検定試験)受験
- ③中国語・英語のアニメDVD
- ④台湾の友達と接点を持ち続ける
■マイルストーンを決める
- 小学生の間(3年間)に、HSK4級〜5級もしくは中国語検定3級取得を目指す
■「なぜ中国語を習うのか」を親自身の中で明確にする
- ①台湾生活の中で、次女が外国語好きだと分かったから、強みを伸ばしたい。
- ②英語は当たり前の時代。英語プラス他の言語ができると強い。
- ③発音は子どものうちの方が身につきやすい
- ④中国は「異形の大国」。台湾は日本の最重要パートナー。二つの国とコミュニケーションが取れる言葉が中国語であり、日本人で中国語人材は重要。
■子どもが楽しく学べているかが一番重要
最近は、駐在などで中国語圏に住んでいた人だけでなく、日本でゼロから中国語を習っている子も増えています。
私たちの子ども世代が、しっかりとした日本語の土台の上に、英語プラス中国語を身につけて、真に国際的な日本人として活躍していってくれたらうれしいですね。











[…] 【子どもの習い事】台湾・中国在住後、日本で子どもの中国語力を維持する方法 […]
[…] […]