
台湾について少し深く知りたい。
台湾の元総統・李登輝氏の著書って、たくさんあるけど、どれから読んだらいいかな?
という疑問にお答えします。
■本記事の内容
- 最初の一冊としておすすめなのは、『新・台湾の主張』(李登輝・2015年)
- 『新・台湾の主張』をおすすめする理由
- 『新・台湾の主張』目次紹介
- 李登輝氏が色々な著書で繰り返し述べておられること
- 『新・台湾の主張』から5年経った現在
- まとめ
■最初の一冊としてお勧めなのは、『新・台湾の主張』
本記事を書いている私が、台湾について知ったのは大学時代(20年以上前)です。
大学で中国語を学んでいましたが、中国(中華人民共和国)について知れば知るほど病み、挫折気味な時でした。
そんな時、李登輝元総統の著書『台湾の主張』(1998年出版)を読んで、衝撃を受けました。
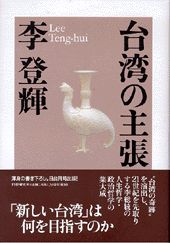
その後、中国や台湾とは関係のない仕事をしていましたが、李登輝元総統の著書から受けた影響はとても大きかったです。
日本人として今まで知らなかった日本の近現代史と台湾との関係を知ったことで、学校教育では習わなかった歴史観を得ることができました。
『新・台湾の主張』は、ベストセラーになった『台湾の主張』から16年経って、2014年9月に李登輝元総統が、5年ぶりに来日された後、2015年1月に出版された新書です。

新書ということもあり、今までの李登輝氏の著書のエッセンスがまとまったような内容になっています。
この一冊で、李登輝元台湾総統の基本的な哲学や、日本へのメッセージ、台湾へのメッセージを知ることができます。
■『新・台湾の主張』をおすすめする理由

本書を読むと2つのことがわかります。
- 日本が目指す未来がわかる
- 台湾の今がわかる
①日本が目指す未来がわかる

本書の「はじめに」で、
日台の絆は歴史に基づくものだ。しかし、過去の日台が歩んできた道について知らない人がいかに多いことか。日本と台湾は生命(運命)共同体である。日本がよくなれば台湾もよくなり、その反対も然りである。
と書かれています。
『台湾の主張』が出版されてから16年経ち、日本と台湾の交流は深まってはいますが、日本人の台湾への理解は、まだまだ十分とは言えないのです。
さらに、「はじめに」には、
台湾の未来のための方向性をここに改めて示すこととし、本書を『新・台湾の主張』とした
と書かれています。
「台湾の未来のために」と書かれたこの本が、日本語で出版されていることの意味はなんでしょうか。
李登輝元総統は、日本人にも、この「台湾の未来のための方向性」を理解してもらいたい、力になってもらいたい、と思ってらっしゃるのだと思います。
私たち日本人が台湾に理解を深めることは、台湾はもちろん、日本の未来のための方向性に直結するからです。
②台湾の今がわかる

「はじめに」は日本人へのメッセージになっていますが、一方、「あとがきに代えて」は台湾人へのメッセージになっています。
本書が出された2015年は、2012年に再選された国民党の馬英九総統の時代です。
馬英九総統時代(2008年から2016年)は、台湾が急速に中国(中華人民共和国)に接近し、台湾の経済力や、民主化が後退した時代でした。

李登輝元総統は、本書で、馬英九総統に対して「台湾の未来のために辞任せよ」と喝破されています。
そして、
台湾はもはや変わらなければならない時を迎えている。
台湾の運命を握っているのはわれわれだ。
われわれは前へ進みたいのか、それとも後退して谷底へ落ちたいのか。
中略
民主台湾を永遠ならしめるために、不屈の精神でわれわれは進まなければならない。
p200-p201
という言葉で本書を締めくくっておられます。
この言葉から、さらに5年の時が経った現在。
2019年から香港で起こっている「反中デモ」の戦いを目の当たりにした台湾人は、「後退して谷底に落ちる」手前で、踏みとどまったのです。

今回2020年1月の台湾総統選挙での結果(民進党・蔡英文総統の圧勝)は、「近代化と民主化の過程で育まれた『台湾精神』」(p197)が失われていなかったことを証明しました。
蔡英文さん、過去最多得票を獲得し当選👏おめでたい㊗️
— fang🏃♀️ (@fangyori) January 11, 2020
投票前の昨日10日に行われた感動的な選挙演説を遅ればせながらですがどうぞ。
中国語の文字起こしと日本語の字幕を作成しました。 pic.twitter.com/rqcgnOd33S
蔡英文総統は、選挙戦最終日の演説で、
「民主は空から降ってきたものではなく、これまで無数の戦いがあり、多くの人の犠牲により、ついにこのような民主的な生活がここに、この地に根付いたのだ」
と述べています(筆者抄訳)。
まさに、
台湾の近現代〜日本統治時代を経て、中華民国になって苦難の時代(1945年〜1988)から、李登輝元総統が進めた民主化の道(1988〜)、この長い戦いの末に、今の台湾があるのです。
すでに97歳になられる李登輝元総統は、今の台湾の若者から見ても、一世代前の方かもしれません。
でも、その精神は、台湾の若者たちに確実に引き継がれているのだと思います。
『新・台湾の主張』を読めば、今回の台湾選挙をはじめ、台湾への理解が深まります。
■『新・台湾の主張』目次紹介
第一章:日本精神に学ぶ
- 映画『KANO』のこと
- 台湾近代化の基礎を築いた後藤新平
- 新渡戸稲造による製糖業発展の基本方針
- 「嘉南大圳」の父、八田與一
- 私の生き方に影響を与えた本
- 「武士道」―日本人の精神の道徳規範
- 戦死六十二年後、靖国神社で兄と再会
- 日本は英霊の魂をもっと大切にすべき
- 新渡戸稲造と後藤新平に学んだ信仰と信念の大切さ など
第二章:台湾民主化への道
- 台湾人を恐怖の底に陥れた二・二八事件
- 三十八年間に及んだ戒厳令
- 総統になったのは「歴史の偶然」
- 「台湾人に生まれた悲哀」
- 「台湾人の総統」を選ぶ直接選挙
- 「特殊な国と国の関係」発言の衝撃
- 台湾大地震という試練
- 真っ先に到着した日本の救助隊 など
第三章:新台湾人の時代へ
- 経験不足を露呈した民進党政権
- 台湾の国家正常化とは何か
- 民主化進展を阻む台湾固有の問題
- 雨中の演説で馬総統を批判
- ヒマワリ学生運動が起こる
- 中国の正確な姿を伝えるのが台湾の役割
- 「新台湾人」というコンセプト
- 台湾は「民主人」の共和国であるべき など
第四章:日本と台湾の国防論
- 台湾の地政学的な重要性
- 残念な日本の姿勢
- 日台間に領土問題は存在しない
- 日本の最大の課題は憲法改正
- 東日本大震災での痛恨事
- あまりに嘆かわしい日本政府の対応
- 「台湾は中国の一部」がいかに暴論か
- 台湾人が感動した安倍首相の「友人」発言
- 「台湾加油」「日本加油」
- 日台の絆は永遠に など
■李登輝氏が色々な著書で繰り返し述べておられること
- 日本統治時代(1895年〜1945年)の50年間、日本は台湾を近代化させた。
- 自分の人生に一番影響を与えたのは、日本時代の教育だった。
- 日本統治時代に受けた教育によって台湾人は「日本精神(勇気、誠実、勤勉、奉公、自己犠牲、責任感、遵法、清潔など)」を身につけることができ、それによって今の台湾がある。
- 「日本精神」を、日本人も台湾人も取り戻すことが大切である。
- 日本はアジア、世界のリーダーとしての気概を持て。
- 日台の絆は永遠である。
これらは、『新・台湾の主張』でも述べられていて、一貫して李登輝元総統が、日本人へのメッセージとして発してくださっていることです。
■『新・台湾の主張』から5年経った現在

先日、台湾に親しみを感じる日本人が、過去最多になったというニュースがありました。
そして、日本が好きな台湾人も過去最高となっています。
先日の台湾総統選挙では、Twitterで#Taiwan #Taiwan electionなどがトレンド入りするくらい、日本でも注目され、多くの日本人が、台湾の自由・民主・人権を守る戦いを応援しました。
日本と台湾の関係は非常に良好と言えます。
しかし、いまだに国家として日本は台湾(中華民国)とは断交したまま。
日本は台湾を国と認めていない状態です。
日本が台湾と国交を回復するためにも、一人でも多くの日本人が、日本と台湾の歴史を知り、より深く協力していかなければならない時です。
本書を多くの方に読んでいただくことが大事だと、改めて思います。
■まとめ

本記事では、台湾について知りたい方に、李登輝元総統の著書『新・台湾の主張』をご紹介しました。
- 『新・台湾の主張』をおすすめする理由
- 『新・台湾の主張』目次紹介
- 李登輝氏が色々な著書で繰り返し述べておられること
- 『新・台湾の主張』から5年経った現在
実は、2014年9月、なんと李登輝氏が来日・講演されるということを知って、私も参加申し込みしました。
ちょうど長男を妊娠中で、大きなお腹で、大阪での講演会に参加したのをよく覚えています。
そして、講演会では、李登輝元総統の「誠實自然」という揮毫(コピー)をいただきました。
これは、おそらくたくさんの方が持ってらっしゃるものだとは思いますが、額に入れて家宝のように飾っています。
2014年9月来日公演の後、出版された『新・台湾の主張』を読んで、「22歳まで日本人だった」李登輝元総統から、私たちは多くのことを学ばせていただいていると、あらためて感謝の思いでいっぱいでした。
台湾に関心を持ってらっしゃる方も、まだそんなに知らない方も、ぜひ本書を読んでみてください。
日本に「きょうだい」とも言える国があることに感動すると思います。









